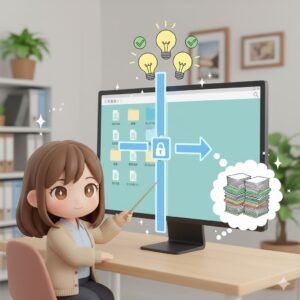あなたのパソコンの「ダウンロード」フォルダや「ドキュメント」フォルダ、こんなことになっていませんか?
請求書.pdf請求書(1).pdf請求書(2).pdfA社見積書(最新).docxA社見積書(最終版)_修正.docxBook1.xlsxコピー ~ 2024年10月売上.xlsx
紙の書類を減らすために「ペーパーレス化」を進めたはずなのに、パソコンの中が、現実の机の上以上に散らかってしまっている…。
必要なPDFが1枚見つからないせいで、メールを何十件も遡ったり、フォルダを一つひとつ開けて中身を確認したり。そんな「探し物」に、毎日どれだけの時間を使っているでしょうか。
こんにちは。AIやITを活用して、面倒なデジタル業務やデータを整理するデジタル整理アドバイザー「らくらスタイル」です。
私自身、完璧主義でありながら、根はものすごく「めんどくがり」。
だから、請求書(1).pdf のようなファイル名が存在する状態は、それだけでストレスを感じてしまいます。
かといって、ファイルを保存するたびに「完璧な分類」を考えるのも、それはそれで面倒で続かない…。
この「完璧」と「面倒」のジレンマを抱える多くの人にとって、「デジタル書類の整理」は永遠の課題かもしれません。
今日は、この永遠の課題に終止符を打つための、「らくらスタイル」流ファイリング術をお話しします。
一度「仕組み」を作ってしまえば、あとはそれに乗っかるだけ。あなたが二度と「あの書類どこだっけ?」と悩まなくなるための、究極に「楽」なルールです。
なぜ、デジタル書類は「紙」以上に散らかるのか?
そもそも、なぜデジタルデータはこんなにも散らかりやすいのでしょうか。
それは、デジタルと紙の「決定的な違い」にあります。
違い1:物理的な「痛み」がない
紙の書類は、増えれば増えるほど「場所」を取ります。
机の上は狭くなり、ファイルキャビネットはパンパンになる。物理的に邪魔になるので、私たちは「そろそろ整理しないとヤバい」と「痛み」を感じます。
しかし、デジタルデータはどうでしょう?
請求書.pdf が1枚あろうと100枚あろうと、パソコンのデスクトップが狭くなるわけではありません。
ハードディスクの容量(ストレージ)が許す限り、無限に溜め込めてしまいます。
この「痛みのなさ」が、整理整頓のタイミングを失わせる第一の原因です。
違い2:簡単に「複製」できてしまう
「このファイル、こっちのフォルダにも一応コピーしておこう」
こんなふうに、紙では考えられないほど簡単に「複製」ができてしまいます。
その結果、「最新」と「最終」と「コピー」が乱立し、どれが「正本」なのか、作った本人でさえ分からなくなるという悲劇が起こります。
めんどくさがりの私たちがやりがちな「とりあえず保存」と「とりあえずコピー」が、パソコンの中を「紙」以上にカオスな状態にしてしまうのです。
「探す時間」こそ最大のムダ!ファイリングのゴールとは
では、私たちは何を目指して整理すれば良いのでしょうか?
完璧主義な人ほど、「博物館の展示のように美しく分類すること」をゴールにしがちです。
でも、ちょっと待ってください。
「らくらスタイル」が目指すゴールは、そこではありません。
私たちが目指すゴールは、ただ一つ。
「必要な書類(データ)を、必要な時に、30秒(あるいは3クリック)で見つけ出せること」
です。
いくら美しく分類されていても、見つけるまでに5分かかっていたら、それは「失敗した整理」です。
逆に、多少雑に見えても、検索一発で0.5秒で見つかるなら、それは「大成功した整理」なのです。
「めんどくがり」だからこそ、この「探す時間」という最大のムダを徹底的に排除したい。
そのために必要なのが、「保存場所(住所)」と「命名規則(名前)」の2大ルールなのです。
デジタルファイリングの「2大原則」
「探せる」状態にするために必要なのは、たった2つのことです。
- 原則1:保存場所(住所)を固定化する「どこにしまったか」が明確であること。
- 原則2:命名規則(名前)を統一する「何という名前でしまったか」が明確であること。
これは、11月9日の記事(フォルダ階層)と11月10日の記事(命名規則)でお話ししたことの総集編であり、PDF・Word・Excelという「デジタル書類」に特化した実践編です。
この2つさえ守れば、あなたはもう迷いません。
原則1:「保存場所」は「業務(ジャンル)」で仕切る
まずは「住所」を決めましょう。
多くの人が、ダウンロード フォルダや ドキュメント フォルダ(マイドキュメント)に、あらゆる種類のPDFやWordファイルを「ごちゃ混ぜ」に放り込んでいます。
(ドキュメント フォルダの最適解については、明日の記事で詳しくお話ししますね)
これでは、探せるわけがありません。
「ドキュメント」フォルダを、あなたの「仕事のファイルキャビネット」だと考えて、中を「引き出し」と「仕切り箱」で分けていきます。
「ドキュメント」フォルダ内の3階層ルール実践(書類編)
ここでも、11月9日の記事でお伝えした「3階層ルール」が最強の武器になります。
1階層目(タンス)
まずは、一番大きな「タンス」を決めます。
C:\Users\YourName\Documents(ドキュメント)フォルダの中に…01_仕事02_プライベート03_学習99_一時保管(←11月11日の記事参照)
2階層目(引き出し)
次に、「仕事」タンスの中を「引き出し」で分けます。
ここが「書類」ファイリングのキモです。
01_仕事フォルダの中に…01_経理・総務(請求書、見積控、契約書、届出書類など)02_取引先(顧客ごと、プロジェクトごとの資料)03_マーケティング(広報資料、Webサイト関連、広告データなど)04_社内資料(議事録、マニュアル、テンプレートなど)
3階層目(仕切り箱)
最後に、「引き出し」の中を「仕切り箱」で分けます。
01_経理・総務フォルダの中に…請求書(受領)請求書(発行控)見積書(発行控)契約書
02_取引先フォルダの中に…A社Bプロジェクト
どうでしょう?
これで、例えば「A社から受け取った請求書」は、
01_仕事 → 01_経理・総務 → 請求書(受領)
という「住所」が確定しました。
もう「どこに保存しよう?」と迷うことはありません。
原則2:「命名規則」は検索キーワードの「先読み」
さて、完璧な「住所」が決まりました。
次はその「表札(名前)」、つまり「ファイル名」です。
11月10日の記事で「日付」「プロジェクト名」「バージョン」が重要だとお話ししましたが、「デジタル書類」の場合は、この順番が非常に重要になります。
なぜなら、「後から探すとき、何で探すか?」を先読みして、ファイル名の「先頭」に持ってくる必要があるからです。
書類の黄金律:「日付」+「取引先名」+「書類の種類」
「らくらスタイル」が推奨する、デジタル書類の最強の命名規則は、この順番です。
[日付]_[取引先名]_[書類の種類]_[バージョン].拡張子
なぜ、この順番なのか?
それは、フォルダ内で名前順に並べたときに、最も見やすくなるからです。
- まず「日付」で、時系列に並びます。
- 同じ日付なら、次に「取引先名」の順(あいうえお順)で並びます。
- 同じ取引先なら、次に「書類の種類」で並びます。
これが、人間にとってもパソコンにとっても、最も「楽」で、最もミスが少ない並び順なのです。
実践!書類別・命名規則ガイド
では、PDF、Word、Excel、それぞれのケースで見ていきましょう。
PDF(主に「受け取る」か「完成形」の書類)の場合
PDFは、メールで受け取ったり、WordやExcelから書き出して「完成!」としたりする書類です。
受け取ったときのファイル名が invoice_12345.pdf のようになっていることが多いですが、これをそのまま保存してはいけません。
めんどくさいですが、この「一手間」が、未来の自分を救います。
必ず、先ほどの黄金律に沿って「リネーム(名前の変更)」します。
- 保存場所:
01_仕事/01_経理・総務/請求書(受領)/ - ファイル名:
20241114_A社_請求書.pdf - 保存場所:
01_仕事/02_取引先/Bプロジェクト/ - ファイル名:
20241114_Bプロジェクト_契約書(捺印済).pdf
Word(主に「作成・編集」する文書)の場合
Wordは、途中で何度も修正が入る「生きた」文書です。
ここで重要になるのが、「バージョン管理」です。
「(最新)」や「(最終版)」は、11月10日の記事でお話しした通り、混乱の元なので絶対禁止です。
_v1 _v2 _v3 …と、末尾にバージョンを付けます。
- 保存場所:
01_仕事/02_取引先/A社/ - ファイル名: 20241114_A社_提案資料_v2.docx(v1 は昨日の版、v2 が今日修正した最新版、という意味)
- 保存場所:
01_仕事/04_社内資料/議事録/ - ファイル名:
20241114_定例ミーティング議事録_v1.docx
Excel(主に「管理・更新」する表)の場合
Excelは、Wordとは少し性質が異なります。
「バージョン」を重ねるファイル(例:タスク管理表)と、ひと月のデータをまとめる「月次」ファイル(例:売上管理表)などがあるからです。
<月次・年次で更新する表>
ファイル名に「いつのデータか」が分かるようにします。
- 保存場所:
01_仕事/01_経理・総務/ - ファイル名:
202411_売上管理表.xlsx(11月分のデータ) - ファイル名:
2024_顧客リスト.xlsx(2024年版のデータ)
<プロジェクトで進行する表>
これはWordと同じく、バージョン管理を使います。
- 保存場所:
01_仕事/02_取引先/Bプロジェクト/ - ファイル名: Bプロジェクト_タスク管理表_v3.xlsx(※この場合、日付はファイル名に入れず、v3 が最新だと判断します)
このように、「書類の性質」によってルールを使い分けるのがコツです。
めんどくさがりのための「ワンポイント・テクニック」
ルールは決まりました。
でも、めんどくさがりの私たちは、「もしルールを破りたくなったら…」「もっと楽したい…」と考えてしまいますよね。
そんなあなたのための、「保険」であり「飛び道具」となるテクニックをご紹介します。
テクニック1:PDFは「OCR処理」をかけて保存する
これが最強の「保険」です。
「OCR(オーシーアール)」とは、画像として保存されている文字を、パソコンが認識できる「テキスト文字」に変換する技術のことです。(Optical Character Recognition:光学文字認識)
最近のスキャナや、Adobe AcrobatのようなPDF編集ソフト、一部のクラウドストレージには、このOCR機能がついています。
(らくらスタイルでも、OCR導入のご相談は非常に多いです)
これの何がすごいのか?
例えば、20241114_A社_請求書.pdf と完璧な名前を付け忘れて、invoice.pdf のまま保存してしまったとします。
でも、このPDFにOCR処理がかかっていれば、パソコンの検索機能で「A社」とか「請求番号 12345」と、PDFの中身の文字で検索して、invoice.pdf を見つけ出すことができるのです!
ファイル名を付けるのが面倒な時でも、OCRさえかけておけば「中身検索」という保険が効く。これは、めんどくさがりな完璧主義者にとって、最高の「楽」だと思いませんか?
テクニック2:AI検索を「飼いならす」
最近のパソコン(WindowsのCopilotやMacのSpotlight)は、AIを搭載し、検索機能が非常に賢くなっています。
「A社の先月の請求書」と話しかけるだけで、見つけてくれる未来も遠くありません。
私たちらくらスタイルも、新潟という拠点で、日々AI活用の研究とご提案を進めています。
しかし、覚えておいてください。
AIも、整理されていないデータ(ゴミ屋敷)の中からは、正しい答えを見つけられません。
AIが 202410_A社_請求書.pdf を「先月のA社の請求書」だと認識するためには、私たちが「01_経理・総務/請求書(受領)」という「住所」に置き、「202410_A社_請求書」という「名前」を付けてあげる必要があるのです。
AIに「楽」をさせてもらうために、私たち人間は「最低限のルール(住所と名前)」を守る。これがAI時代の上手な付き合い方です。
テクニック3:「一時保管」フォルダと「正規の場所」を使い分ける
11月11日の記事でご紹介した「99_一時保管」フォルダを、ここでも活用します。
- WordやExcelで「作業中」のファイル:まだ完成していない、v1 にもなっていない「下書き」は、99_一時保管 フォルダで作業します。正規のキャビネット(01_仕事)を汚しません。
- PDFを「とりあえず」受け取った時:リネームして正規の場所に保存するのが面倒な時は、一旦 99_一時保管 フォルダに放り込みます。
- そして、週に一度(金曜の午後など)、
99_一時保管フォルダを開き、完璧な「住所」と「名前」を与えてファイリングします。
これで、「保存の面倒くささ」と「探す面倒くささ」を分離して、両方を解決できますね。
まとめ:デジタル書類は「仕組み」で整理しよう
紙よりも散らかりやすいデジタル書類だからこそ、「気合」や「完璧主義」で整理しようとすると挫折します。
めんどくさがりな私たちでも続く「仕組み」を作ってしまうことが、唯一の解決策です。
- ゴールは「検索性」。 30秒で見つかることが正義です。
- 原則1:「保存場所(住所)」を決める。
ドキュメントフォルダ内を「3階層」で仕切ります。(例:仕事/経理/請求書)
- 原則2:「命名規則(名前)」を統一する。
- 黄金律は
[日付]_[取引先名]_[書類の種類]_[バージョン]
- 黄金律は
- PDF・Word・Excelでルールを使い分ける。
- PDFは「リネーム」、Wordは「バージョン」、Excelは「月次 or バージョン」
- 「OCR」や「一時保管」を活用し、「楽」をするための保険をかける。
まずは、今日受け取ったPDF 1枚を、このルールでリネームして、決めた場所に保存することから始めてみませんか?
今日のひとこと
「PDFをちょっとだけ直したいのに、専用のソフト(Acrobatなど)がなくて困る!」
そんな経験はありませんか?
実は、最新の Microsoft Word は、PDFを読み込んで、Word文書(.docx)として編集できる機能が備わっています。
Wordで「開く」からPDFファイルを選ぶだけ。
レイアウトが完璧に再現されるとは限りませんが、テキストのちょっとした修正やコピーなら、これで十分対応できます。わざわざPDF編集ソフトを買わなくても「楽」ができる、覚えておくと便利な小技ですよ。
個人的には「PDF-XChage Viewer」を愛用しています。パワポのような感覚で追記出来るので便利です。
らくらスタイルは「日常をもっと楽に、楽しく」を目指して、ご相談内容に合わせてオーダーメイドのお手伝いをいたします。気軽にご相談ください
明日のタイトルは
「散らかりがちな「ドキュメント(マイドキュメント)」フォルダの最適解」
です。お楽しみに!
※内容が変更になった場合はご容赦ください。
#らくらスタイル #デジタル整理 #パソコン #ファイル管理 #命名規則 #PDF #Word #Excel #ファイリング #業務効率化 #パソコン初心者 #新潟 #AI #データ整理 #OCR